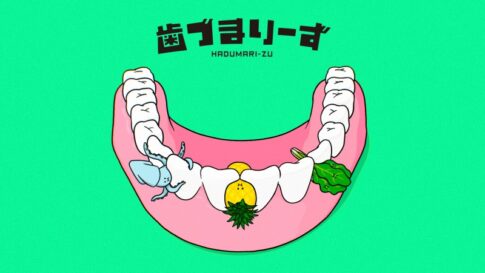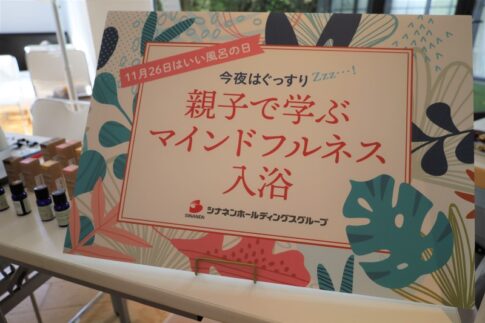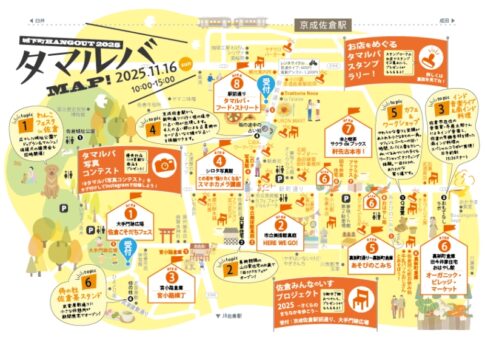ゲームの世界が、いま新しい形の「共生」の場になりつつあります。
年齢や性別、そして身体の違いを越えて、誰もが同じフィールドで楽しめる——それが「eスポーツ」です。近年では、体に不自由のある方も参加できるよう、環境や機器を整え、支援する人を育てる動きが全国で広がっています。
2025年12月7日(日)、名古屋で開催される支援者育成セミナーもその一つです。日本eスポーツ協会を中心に、医療や福祉の分野と連携しながら、障がいのある方が安心してプレイできるような知識や方法を学ぶ場が設けられます。特別なコントローラーを使った体験や、支援の仕方を考える実践的な内容が予定されており、参加者には修了証が発行されます。
ゲームを「競う」だけでなく、「つなぐ」ものとして育てていく——。
eスポーツが持つ可能性を通して、人と人とが支え合う社会のかたちが、少しずつ見え始めています。
eスポーツが生み出す“ハンデのないフィールド”

「eスポーツ」という言葉を耳にする機会が増えました。
ゲームを単なる遊びではなく、競技として楽しむ文化はすでに世界中に広がっています。
その最大の特徴は、年齢や性別、体の状態といった“違い”を越えて、誰もが同じ舞台に立てる点にあります。
たとえば、車いすを使っている人も、手足の動きに制限がある人も、ゲームコントローラーを少し工夫するだけで同じ試合に参加できます。画面の中では、フィジカルの差が勝敗を決めるわけではなく、反応の速さや戦略、チームワークが問われます。そこには「できないこと」よりも、「どうすれば一緒に楽しめるか」を考える前向きな発想があります。
実際に、全国では障がいのある人たちがeスポーツを通じて交流したり、イベントに出場したりする動きが広がっています。ゲームをきっかけに、学校や職場以外のつながりが生まれ、社会との接点を取り戻したという声も少なくありません。
プレイヤーとしての喜びはもちろん、「同じ空間で一緒に遊ぶ」という経験が、何より大きな力になっています。
しかし、こうした活動がすべての地域で当たり前に行われているわけではありません。
障がいに合わせた操作機器の用意や、プレイをサポートする人材はまだまだ不足しています。
それでも「誰もが参加できるスポーツ」にするために、eスポーツの現場では少しずつ変化が起きています。
その一つが、今回のような支援者育成の取り組みです。
支援者を育てるセミナーの取り組み

障がいのある方がeスポーツを楽しむためには、ゲームの知識だけでなく、サポートする側の理解と準備も欠かせません。
そうした支援者を育てる場として、日本eスポーツ協会(JESU)が主催する「からだに不自由のある方へのeスポーツ支援者入門セミナー」が開催されます。
会場は名古屋・栄の中日ホール&カンファレンス。全国から支援や教育、福祉の分野に関わる人々が集まる予定です。
このセミナーの目的は、障がいのある方が安心してゲームに参加できる環境を整えること。
単なる座学ではなく、現場で活かせる知識を学べるのが特徴です。
たとえば、ゲームコントローラーのカスタマイズや、アクセシビリティ機器を使った操作体験。
さらに、障がいのあるプレイヤーにどのように声をかけ、どう支援すればストレスなく楽しめるのか、具体的な方法を体験を通じて学びます。
講師を務めるのは、eスポーツ協会の担当者や、医療・福祉分野で活躍する現役の作業療法士です。
機器の使い方を説明するだけでなく、支援者としての姿勢や考え方も重視されます。
「どうすれば一緒に楽しめるか」「相手の気持ちを理解するには何が必要か」。
支援の本質を学ぶこの場は、単なる技術講習を超えた、人と人との関係づくりの学びの時間でもあります。
セミナーの最後には、参加者全員に修了証が発行されます。
経験の有無を問わず、誰でも“支援者”として第一歩を踏み出せるよう設計されている点も、この取り組みの魅力です。
eスポーツを通じて「支える人」を増やしていくことが、結果として「楽しむ人」を広げていくことにつながっていきます。
福祉とテクノロジーがつなぐ未来

eスポーツの広がりの背景には、テクノロジーの進化があります。
以前は、障がいを持つ方がゲームをプレイするためには多くの制約がありましたが、いまは一人ひとりの身体の状態に合わせて使える機器が次々と登場しています。
ボタンの位置を変えられるコントローラーや、わずかな手の動き、あるいは目の動きで操作できるデバイスも開発され、誰もが同じように“プレイヤー”として参加できる環境が整いつつあります。
こうした技術を活かしながら、社会全体で支え合う仕組みをつくることを目指しているのが、日本eスポーツ協会(JESU)です。
協会はeスポーツの振興だけでなく、教育や医療、福祉など幅広い分野との連携にも力を入れています。
障がいを持つ方の支援を通じて、スポーツの可能性を社会に広げていく活動を続けています。
たとえば、eスポーツをきっかけにリハビリを続けるモチベーションを取り戻したり、在宅生活の中で他者との交流が増えたりするなど、実際に変化を感じる人も増えています。
プレイすることで得られる「達成感」や「一体感」は、身体の制約を超えて心を動かす力があります。
その裏側には、支援する人たちの努力と、テクノロジーの進歩が欠かせません。
JESUの理念には、「夢をつくる」「産業をつくる」「社会に応える」という言葉があります。
これは単なるスローガンではなく、eスポーツを通じて社会をより良くしていくという強い意志を示しています。
今回のセミナーも、その理念を具体的な形にした取り組みのひとつです。
福祉とテクノロジーが出会うことで、誰もが主役になれる未来が少しずつ現実のものとなりつつあります。
共生社会への一歩として
eスポーツは、今や「競うためのゲーム」から「つながるための文化」へと進化を遂げています。
プレイヤーや支援者、開発者、そして観客――そこに関わるすべての人が、それぞれの立場でこの新しいスポーツを形づけています。
障がいの有無に関係なく、同じ画面を見つめながら笑い合い、拍手を送り合う光景は、まさに“共生社会”の縮図といえるでしょう。
今回のセミナーのように、支援する側の理解を深める活動が増えていけば、「誰かを特別扱いする支援」ではなく、「誰もが自然に参加できる環境」が整っていきます。
その小さな積み重ねが、やがて社会全体の意識を少しずつ変えていくはずです。
テクノロジーの進歩が生み出したこの“新しいスポーツ”は、単に競技の枠を越え、人と人とをつなぐ温かな力を秘めています。
名古屋で行われる今回の取り組みも、その一歩となるものです。
eスポーツを通じて「誰もが主役になれる社会」を目指す動きは、これからさらに広がっていくでしょう。
ゲームの画面の向こうにあるのは、勝敗ではなく、人の想いと支え合い。
その輪が少しずつ広がっていく未来を、多くの人がきっと見つめています。
【主催・共催】
一般社団法人日本eスポーツ協会
一般社団法人愛知eスポーツ連合
公式サイト:https://jesu.or.jp